「子どもの歯並びが気になるけど、これって顎が小さいから?」
「自分の二重顎やフェイスラインの崩れ、実は顎の大きさが関係しているのかも…」
顎が小さいと歯がきれいに並ぶスペースが足りず、歯並びが乱れやすくなったり噛み合わせや発音、顔の印象や口呼吸など、さまざまな影響が出てきたりすることがあります。
本記事では、顎が小さいことで起こりやすい問題とその原因、子どもと大人それぞれに合った対策や治療法について、わかりやすく解説しています。
「矯正が必要かどうか迷っている」「生活習慣で改善できることがあるのか知りたい」という方は、ぜひ最後までお読みください。
顎が小さいと歯並びは悪くなる?

顎が小さい人は、永久歯がきれいに並ぶための骨の幅が不足し、歯がまっすぐ生えずに重なったりねじれたりしがちで、歯並びが悪くなる傾向にあります。
実際、上の歯が前に出る出っ歯や歯がガタガタになったり、下の歯が上の歯より前に出たりするなどの噛み合わせ異常が高い頻度で見られます。
ただし、顎が小さい人すべてが歯並びに問題を抱えるとは限りません。
歯並びは遺伝的な骨格の特徴だけでなく、舌で歯を押す癖、指しゃぶりの長期化、うつ伏せ寝、頬杖などの習慣的動作の影響も受けます。
顎が小さくなってしまう理由

顎が小さいのは「生まれつき」と思われがちですが、実は成長過程での環境や生活習慣が深く関係していることも少なくありません。
ここでは、顎が小さくなる主な理由として以下の2つに分けて詳しく解説します。
遺伝によるケース
顎の骨格は、両親や祖父母からの遺伝によって影響を受けやすい部位です。
たとえば、両親のどちらかに下顎が小さく奥まった骨格の特徴がある場合、子どもにも同じような傾向が見られやすくなります。
矯正治療を始めるか迷っている場合には、子どもの口元とともに親や祖父母の歯並びや骨格を写真などで比較してみましょう。
それにより、歯が並ぶスペースの不足や噛み合わせのズレが将来的に起こる可能性を予測しやすくなります。
成長過程で小さくなるケース
離乳期や幼児期に、ヨーグルト、プリンといった咀嚼が少なくても食べられるメニューを中心に食べていると、顎の筋肉を十分に使わないまま食事が終わりがちです。
こうした食生活が続くと、1食あたりの咀嚼回数が150回未満になることもあり、顎の骨が成長するための刺激が不足します。
さらに、以下のような習慣が3歳以降も続く場合、顎の発達に悪影響が出る可能性が高まります。
- 指しゃぶりを毎晩行っている
- 鼻詰まりやアレルギーで1日中口が開いている
- 舌がいつも下の前歯の裏に当たっている
- 頬杖をついたままテレビやスマホを見る習慣がある
また、椅子に座るときに背中を丸め、顎を引いた姿勢が習慣になっている子どもも、顎の位置が後ろにずれたまま骨格が形成されます。
こうした姿勢や口まわりの癖が続くと、上下の噛み合わせが合わなくなったり、口が常に開いている状態が習慣化したりするため、気づいた時点で声かけや生活環境の見直しをしていきましょう。
顎が小さいことによるデメリット

ここでは、顎が小さいことで起こりやすい4つの代表的なデメリットについて、具体的にご紹介します。
歯並びが乱れやすい
顎が小さいと、歯が生えるためのスペースが足りず歯がきれいに並ばずに重なったり、斜めに生えたりすることが多くなりがちです。
たとえば、上の前歯から奥歯にかけて左右6本を並べるには約28〜30mmの横幅が必要とされていますが、顎の幅がそれより狭いと歯がまっすぐ生えられず、ねじれてしまう可能性があります。
歯並びが乱れると、見た目に影響するだけでなく上下のかみ合わせにもズレが生じやすくなります。
かみ合わせが悪いと、一部の歯だけに強い力がかかり、その歯がすり減ることで歯ぐきに負担がかかってしまい、炎症や出血につながる可能性すらあるのです。
また、歯が正しく並んでいないと食べものが噛みにくくなるほか発音が不明瞭になるなど、口腔機能にも影響が出やすくなります。
こうしたかみ合わせのズレは、将来的に歯周病や顎関節症のリスクを高める要因のひとつです。
口呼吸になりやすい
上顎の骨が狭いと、それにともなって鼻の中の空気の通り道(鼻腔)も狭くなる傾向があります。
鼻づまりやアレルギー性鼻炎がある子どもの多くは、日中も寝ている間も口で呼吸する習慣がつきやすく、結果的に口の中が乾きやすくなるのです。
唾液には細菌の繁殖を抑える働きがありますが、口腔内が乾燥するとその効果が弱まり虫歯や歯周病の原因菌が増えやすくなります。
さらに、口呼吸では本来鼻がフィルターの役割を果たして取り除いてくれるホコリやウイルス、花粉などがそのまま喉や肺に侵入してしまいます。
結果として、風邪をひきやすい、咳やアレルギー反応が出やすいなどの弊害につながるデメリットがあります。
発音に影響が出やすい
顎が小さいと、舌が動かせる範囲が限られてしまい、言葉を発する際に舌がうまく前歯の裏や上顎に触れられず、特に「さしすせそ」「たちつてと」といった舌先を使う音が不明瞭になりがちです。
実際に、小学校低学年で発音検査に引っかかる子どもは、舌の位置が安定していない特徴があります。
これは、舌小帯(舌の裏の筋)が短いことに加えて顎のスペース不足による可動域の制限が影響しているのが原因です。
加えて、噛む力が弱いためにステーキやナッツ類などの硬い食べ物を避けがちになり、結果的に偏食や栄養バランスの乱れにもつながります。
二重顎が目立ちやすい
顎の骨が十分に発達していないと、顎先から首元までのラインがぼやけて見えやすくなります。顔全体が丸く見えたり、下顎に脂肪がたまりやすくなったりするのもその一因です。
とくに、顎の横幅や前後の厚みが不足している場合は、フェイスラインが崩れやすくなり、二重顎が目立ちやすくなります。
さらに、口呼吸の習慣があると、口が常に開いた状態になりがちです。顎周りの筋肉があまり使われなくなることで、次第に筋力が低下し、皮膚が支えきれずにたるみが生じます。
さらに、1日5〜6時間以上スマートフォンやゲームをしている方は、うつむいた姿勢が続くことで舌骨筋や広頸筋などの顎下の筋肉が緩み、たるみや脂肪の蓄積を助長します。
こうした変化は、横顔の写真や鏡で下からのぞいたときなどに特に目立ちやすく、人によっては大きなコンプレックスになることも少なくありません。
顎を大きく改善する方法
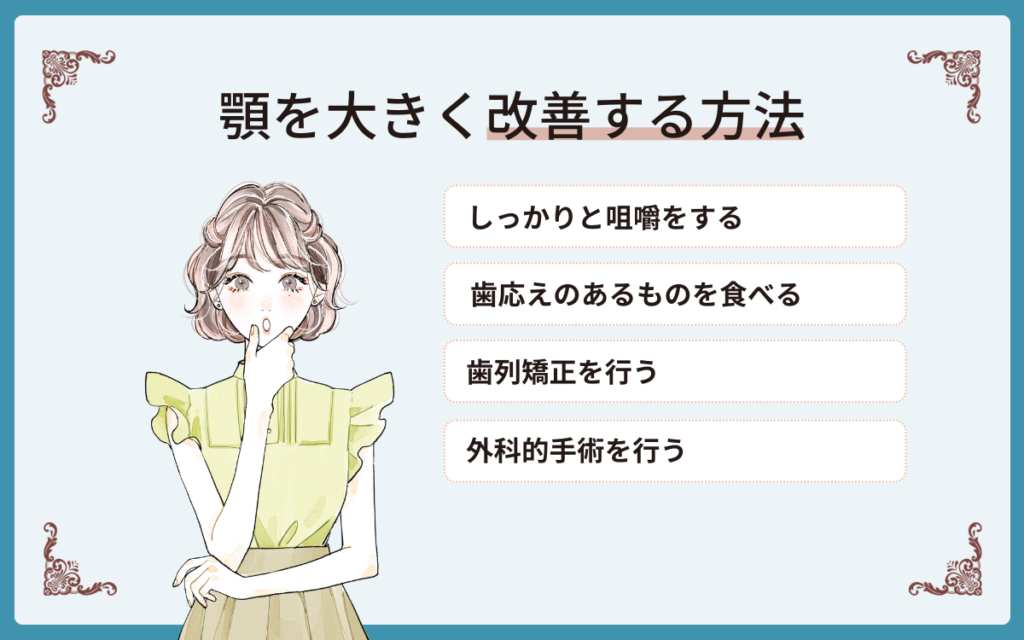
顎の小ささには食生活や日常の習慣も大きく関わっているため、成長期の子どもであれば生活習慣の見直しで改善が見込めます。
また、大人でも矯正や手術といった医療的な方法によって対処することが可能です。
ここでは、日常生活で取り組める予防・改善法から、必要に応じて検討される専門的な治療方法まで、顎を大きく育てたり整えたりするための手段をご紹介します。
しっかりと咀嚼をする
咀嚼は、顎の筋肉や骨に刺激を与え発達を促す働きがあるだけでなく、よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐことが可能です。
これは肥満予防や、子どもの脳の発達にも良い影響を与えると言われています。
1口につき30回以上噛むことを意識するだけでも、咬筋(頬の筋肉)や側頭筋(こめかみの筋肉)がしっかり働き、顎の骨に適度な刺激が伝わります。
ご飯や煮物のように柔らかい料理であっても飲み込む前にしっかり噛むだけで、顎の発育をサポートする効果が期待できるので、しっかりと咀嚼する習慣をつけましょう。
特に5〜8歳は、永久歯が生え始める大切な時期です。この時期に「一口30回噛む」習慣を身につけることで、歯がきれいに並ぶためのスペースが確保しやすくなります。
理想的には、離乳食の頃から「よく噛む」ことを意識させるとよいでしょう。日常の中で「30回噛んでからごっくんしようね」と声をかけることで、自然と咀嚼の習慣が定着していきます。
歯応えのあるものを食べる
顎をしっかり育てるためには、よく噛まないと飲み込めないような「歯応えのある食べもの」を、毎日の食事に少しでも取り入れることが大切です。
たとえば、生のにんじんをスティック状に切ったものや、噛みごたえのある干し芋、皮がしっかり焼けたフランスパンなどは、自然と咀嚼回数が増える食材です。
ほかにも、長く噛んでいられるスルメや、シャキシャキ感を残して調理したれんこんのきんぴら、弾力のある鶏の砂ずりなども、顎の筋肉をよく使うメニューといえます。
また、食後に無糖のガムを10分ほど噛む習慣をつけるのもおすすめです。
ガムを噛むことで顎まわりの筋肉が鍛えられ、同時に唾液の分泌も促されるため、虫歯予防にもつながります。
毎日の中でほんの少し意識するだけでも、将来の歯並びやフェイスラインに差が出てきます。
まずは、無理のない範囲で「よく噛む食材」を選んでみましょう。
歯列矯正を行う
5歳から12歳までの成長期には「床矯正」と呼ばれる拡大装置を使って、上顎や下顎の横幅を広げる治療を行うことができます。
この装置は、入れ歯のような形状で取り外しができ、中央のネジを週に1回程度まわすことで、月に1〜2mmずつ顎を広げていく仕組みです。
通常、この治療は1年〜2年間続けられ、計画的に拡大が進むと将来的に永久歯を抜かずに歯並びを整えられる可能性が高まります。
とくに前歯が生え変わる6〜8歳の時期に開始すると、顎の骨の柔軟性を活かした矯正が可能になります。

外科的手術を行う
18歳以上の成人で、以下のような症状がある場合には外科的矯正手術が検討されます。
- 下顎が後ろに引けていて横顔が「顎なし」に見える
- 上顎が前に出ていて唇が閉じづらい
- 顎が左右にずれており噛み合わせが片側しか合っていない
骨格性の問題に対しては「上下顎骨切り術」という手術が行われ、顎の骨を切って再固定して正しい位置に整えます。
手術は全身麻酔で行われ、約1週間の入院が必要となります。術後は1〜2週間ほど腫れや痛みがありますが、1か月後には社会復帰が可能なケースが多く見られます。
この手術は、顎変形症(がくへんけいしょう)と診断された場合、健康保険が適用され、総額100万円以上かかる費用のうち3割負担で済むことが一般的です。
顎が小さい人が歯列矯正を行うデメリット

ここでは、顎が小さい方が矯正治療を受ける際に知っておきたい代表的なデメリットを3つの視点から解説します。
抜歯が必須となる場合がある
顎の幅が狭く、歯をきれいに並べるためのスペースが足りない場合、第一小臼歯(4番の歯)を上下左右1本ずつ、合計4本抜歯する矯正治療が行われることがあります。
これは成人矯正でよくあるケースで、歯の総本数を減らして並びきらない歯のスペースを確保する方法です。
この抜歯は、歯科医院または口腔外科で局所麻酔を用いて行い、1回の処置で左右どちらか2本を抜歯するのが一般的です。
抜歯自体は10〜20分程度で終わりますが「健康な歯を抜くことに対する不安」や「取り返しがつかない判断を迫られる」と感じる人も多く、カウンセリング段階で治療をためらうケースも見られます。
マウスピース矯正が適用外になる場合がある
透明なマウスピース型矯正(インビザラインなど)は、前歯の軽い重なりや、犬歯が少し前に出ているといった比較的軽度の歯並びに適しています。
1本の歯を2〜3mm程度動かす症例であれば、十分対応可能です。
ただし、以下のような状態ではマウスピースでは対応できず、従来のワイヤー矯正や顎の骨を整える外科矯正が必要になることもあります。
- 前歯が90度以上回転して生えている
- 噛み合わせに大きなズレがある
- 顎が左右にずれているなど、骨格自体のゆがみがある
ワイヤー矯正でも、白や透明の「審美ブラケット」を選べば装置を目立ちにくくすることが可能です。
なお、審美性を重視する場合は、通常のワイヤー矯正に加えて5〜15万円ほどの追加費用がかかることがあります。
小児矯正よりも時間がかかる場合がある
15歳を超えると、顎の骨の成長がほぼ終了しているため「顎を拡大して歯を並べる」というアプローチが難しくなります。
そのため、成人矯正ではスペースを確保するための抜糸を行うか奥歯を後方へ移動させる処置(遠心移動)が行われることがよくあります。
治療工程が複雑になるため、矯正期間は2〜3年に及ぶことが多く、症例によっては4年以上かかることもあります。
また、矯正終了後に歯が元の位置に戻ろうとする「後戻り」を防ぐため、リテーナー(保定装置)を1日12〜20時間装着する期間がさらに1年半〜2年程度必要です。
歯列矯正の種類別比較表
歯列矯正にはいくつかの種類があり、年齢や歯並びの状態、ライフスタイルによって適した方法が異なります。
特に「顎が小さい人」にとっては、どの矯正法が負担を軽減できるか、治療のハードルを下げられるかも重要な視点です。
以下の表では、代表的な3つの矯正法「床矯正」「ワイヤー矯正」「マウスピース矯正」の特徴やメリット・デメリットを一覧で比較しています。
| 歯列矯正の種類 | 床矯正(しょうきょうせい) | ワイヤー矯正 | マウスピース矯正 |
| 対象年齢 | 5〜12歳(成長期) | 小学生高学年〜成人 | 中高生〜成人 |
| 特徴 | 顎の幅を拡大する取り外し式装置 | 歯の表面にブラケットをつけてワイヤーで引っ張る | 透明なマウスピースで少しずつ歯を動かす |
| メリット | ・非抜歯で済む可能性が高い・装着時間の調整ができる | ・重度の歯並びにも対応可・仕上がり精度が高い | ・目立たない・取り外し可能で衛生的 |
| デメリット | ・自己管理が必要・サボると効果が出にくい | ・目立ちやすい・清掃がしにくく虫歯リスクも | ・適応症例が限られる・装着時間の自己管理が必要 |
3つの矯正法には、それぞれメリット・デメリットがありますが「どの治療が正解か」は、顎や歯の状態によって変わります。
たとえば、まだ成長途中であれば「床矯正」で非抜歯のまま顎を広げられることもありますし、大人の場合は「審美性」や「装着感」を重視してマウスピースを選ぶ方も少なくありません。
ただし、骨格のズレや重度の叢生(ガタガタの歯並び)にはワイヤー矯正が必要になることが多いため、まずは歯科医院で相談して見ましょう。
まとめ
顎が小さいことは、歯列の乱れを引き起こす大きな要因の一つです。
歯並びが悪くなると、噛みにくさや発音のしづらさに加え、口呼吸の習慣化による虫歯・歯周病リスクの上昇、フェイスラインの変化といった日常生活への支障が現れます。
こうした問題の背景には、骨格の遺伝的要素だけでなく、やわらかい食事の習慣、咀嚼不足、姿勢の悪さ、慢性的な口呼吸など、複数の環境要因が複雑に絡んでいます。
前歯の重なりや噛み合わせのズレ、口呼吸、滑舌の悪さなどに心当たりがある方は、歯科医院や矯正専門クリニックで相談してみてくださいね。
マウスピース矯正どれにしようか迷ったら、「エミニナル矯正」を受けてみて!

月々3,000円から始められるエミニナル矯正は、「安心」で選ばれるマウスピース矯正です。
近年、不適切なマウスピース矯正治療により、残念な想いをされている方がいます。
治療期間が短く、極端に安価であることを謳うマウスピース矯正がでてきている中で、「歯並びの仕上がり結果が、理想から程遠い。噛み合わせが逆に悪くなった。」「当初伝えられた治療費より、結果大幅に総額が高くなり、途中で治療を断念した」などのお声を聞きます。
これらの問題を解決すべく、エミニナルでは矯正のプロ”矯正ドクター”が100%担当する仕組みを作りました。在籍ドクターの治療経験は500症例以上なので、安心です。
エミニナル矯正の矯正相談では、あなた1人1人の矯正に対する不安を取り除き、そもそもマウスピース矯正が合っているのか?、金額や支払い方法はどのようなものがあるのかを丁寧にお伝えしています。
提携クリニックは全国拡大中です。お近くの提携クリニックはこちらからお探しください。
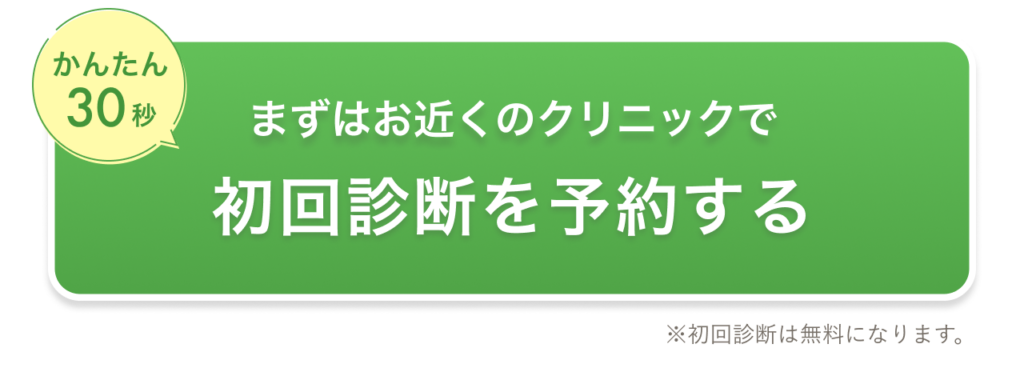
| サービス名 | エミニナル矯正(EMININAL) |
| 目安総額 (軽度〜中度) | 33万円〜66万円 ※自由診療 |
| 初回診断 | 無料 |




